| No.1元茨木川緑地_武士自然歩道_阿武山_摂津峡 |
|
 |
|
<概要>
2019年11月10日(日)は、山を登る会の第1,063回例会に単独で参加した。
スタートは阪急茨木市駅、ゴールは高槻市営バス上(かみ)の口バス停。
この日の目玉は二つある。
一つは、元茨木川緑地と武士(もののふ)自然歩道を歩くこと。
もう一つは、藤原鎌足の墓(貴人の墓)とされる阿武山古墳を訪れ阿武山に登ること。
元茨木川緑地は、下記茨木市のサイトによると、昭和24年に廃川となった全長5キロメートルの元茨木川をグリーンベルトとして整備した緑地帯で「大阪府緑の百選」に選定されている。
元茨木川緑地
茨木には自然歩道として、竜王山・武士・山脈・鉢伏・北山・キリシタンの6コースと東海自然歩道を組み合わせたコースなどがある。
その中の一つ、今回歩いた武士自然歩道は、桑原橋を起点に高槻市との市境を安威川沿いにのぼり、途中、一名「美人山」と呼ばれる阿武山を越え、明智街道を通り竜仙の滝へ抜け、車作大橋までの全長約8キロメートル、所要時間3時間のコース。
【コース】桑原橋バス停~(0.4キロメートル)稲荷神社~(0.8キロメートル)貴人の墓~(0.7キロメートル)阿武山~(1.7キロメートル)阿武山口バス停~(3.9キロメートル、別名:明智街道)竜仙の滝~(0.5キロメートル)★竜仙峡バス停。
★竜仙峡バス停は現在利用不可。
茨木自然歩道を歩く 3
武士(もののふ)自然歩道
Wikipediaによると、阿武山古墳(あぶやまこふん)は、高槻市奈佐原・茨木市安威にある古墳。
国の史跡に指定されている。
阿武山(標高281.1メートル)の山腹に位置する。
昭和初期に地下から古代の貴人の埋葬遺体が発掘され、被葬者を藤原鎌足(中臣鎌足)に比定する説が知られる。
阿武山古墳
この日歩いたコースの内、過去に歩いたことがあるのは、摂津峡公園内の白滝から上の口バス停までの僅かな区間だけで、コースの大半を初めて歩いた。
武士自然歩道は、駅から遠いのでバスに乗った方がアクセスが良い。
その場合、安威バス停又は桑原橋バス停が最寄の停留所となる。
尚、上記茨木市のサイトで紹介されている「竜仙峡バス停」は現在利用出来ない。
(安威川ダム建設工事による道路付け替えの影響で路線は現在休止となっている)
画像は阪急茨木市駅から高槻市営バス上の口バス停までのGPSログを表示。
| |
 |
|
<コース>
阪急茨木市駅9:19_<中央通り>_東本願寺茨木別院前_川立地蔵尊_茨木神社鳥居_<元茨木川緑地>_常夜燈(大峯山上献燈)_石柱(寺の上の樋跡)_石碑(六軒町橋跡)_JR京都線の高架下を潜る_田中橋(交差点)_記念碑(田中橋跡)_茨木川に出合い 三叉路を左折_R171茨木川に架かる春日橋を渡る_西河原西交差点で府道15号茨木亀岡線を北へ_長岡香料前_名神高速道路の高架下を潜る_耳原交番北(交差点)_阪急バス安威(あい)南口バス停前_阪急バス安威バス停前_安威川に架かる長ヶ橋(おさがばし)を渡る_長ヶ橋北詰交差点_道標(←武士(もののふ)自然歩道)・階段を登る_道標(武士自然歩道入口 →阿武山古墳)_分岐で右折(鳥居方向)_鳥居(扁額:阿武山稲荷)_送電線の下を潜る_祠(阿武山稲荷神社)・石碑(稲月大神 旧跡 昭和七年)_道標(→阿武山 山友会)_看板(敷地内立入禁止 大阪学院大学)_分岐を右折するも住宅地 分岐に戻り直進_分岐に立つ道標(←阿武山山頂 桑原橋バス停→ 武士自然歩道)_分岐道標(←阿武山山頂600m / 京大地震観測所400m&阿武山古墳160m→)で右折し阿武山古墳へ_道標(←阿武山古墳0.15km)_分岐道標(←京大地震観測所正門500m バス停薬科大前1.2km&上の池公園2.1km)で左折を見送りフェンスに沿って直進_シャシャンボ(ツツジ科)_説明板(史跡 阿武山古墳)・墓室_分岐道標に戻り阿武山山頂600mへ_説明板(阿武山古墳 貴人の墓)_分岐道標(アセビ峠を右に見送り直進)_眺望地・案内板(高槻市見晴台 中心 市街地)_分岐道標(シルバー用安全迂回路を右に見送り一般者用登山道を直進)_眺望地_分岐で阿武山御神木(榎木)に立ち寄り阿武山山頂へ_分岐で一般者用登山道を直進_道標(←阿武山山頂 / 桑の原橋バス停→ / 武士自然歩道)_阿武山(三等三角点 280.92m 点名:阿武山)_分岐道標で奈佐原古道&阿武山学園&上の池公園方面直進を見送り 北大阪変電所方面へ左折_道標(←北大阪変電所 / 阿武山→)_道標(武士自然歩道)_送電線鉄塔下・看板(砂防指定地)_造成地_府道115号線(西五百住線)三叉路を左折・高槻市営バス停阿武山口前_市営バス停変電所前_分岐道標で府道115号線を離れ左折(左 車作 妙見 / 右 萩谷 道)・(武士自然歩道 ←至阿武山 / 至竜仙の滝→)_道標(←至 竜仙の滝 / 至 阿武山→ / 武士自然歩道)_分岐で林道 車作線を横断_看板(山火事注意 武士自然歩道)_送電線鉄塔下_道標(←至 阿武山 / 至 竜仙の滝→ / 武士自然歩道)_11:46眺望地▲348m付近で昼食12:10_送電線下を潜る_分岐道標(↓車作大橋 / 阿武山→)・道標(山火事注意 東海自然歩道)_看板(火の用心 高槻市消防本部 No.65)_道標(竜仙滝← / 萩谷→ / 東海自然歩道)_獣害対策用ネットに沿って下る_府道115号線(西五百住線)を横断・道標(一般コース← / 健脚コース→ / 東海市自然歩道)・道標(車作大橋→ / 東海自然歩道)_貼紙(クマ注意)_看板(道路幅員狭小のため 車両通行禁止 高槻市)_看板(火の用心 高槻市消防本部 No.72)_道路地図(至 萩谷総合公園 白滝方面へ左折)_山火事注意(東海自然歩道)_道標(東海自然歩道 大阪府・高槻市)・道標(←摂津峡 / 萩谷→)_道標(林道 横峯線)_東海自然歩道道標(至 摂津峡→)_案内板(東海自然歩道)_萩谷総合公園_サッカー場_看板(近くに野球場があります。ファールボールに注意してください。 高槻市 東海自然歩道)_<木道>_東海自然歩道道標(←摂津峡 萩谷↓)_分岐で萩谷連絡道を左に見送り東海自然歩道を直進_沢に架かる石橋を渡る_沢に架かる木橋を渡る_道標(←萩谷 / 白滝→)_白滝_道標(上の口 摂津峡→)_芥川出合い下流方向へ_夫婦岩_案内板(摂津峡)_説明板(摂津峡公園)_慶住院前_芥川に架かる摂津峡橋を渡る_説明板(芥川山城跡)_芥川漁業協同組合前_石柱(名勝 摂津峡)_13:30上(かみ)の口バス停13:34_<高槻市営バス>_13:55JR高槻駅
<メモ>
・参加者: 69名。
・リーダー: T氏
・コース歩行 (阪急茨木市駅~上の口バス停までの所要時間と距離)
歩行距離: 約18.1km。
所要時間: 4時間11分。
・当日歩行 (自宅~自宅までの歩数と歩行時間及び推測距離)
歩数: 30,850歩。
推測距離: 約20.6km。(0.67m×30,850歩=20,669m)
歩行時間: 4時間35分。
画像は集合場所の阪急茨木市駅で9時頃撮影。
駅の北側ということもあるがなんだか薄暗い。
| |
 |
|
この日歩くコースについてTリーダーから説明を聞く。
予定では歩く距離は18kmで長丁場となる見込み。
私のスマホによると実際に歩いた距離は18.1kmでほとんど差がなかった。
| |
 |
|
集合場所は2階なので地上へ降りて駅から西方向に向かって中央通りを歩く。
尚、この駅前に立つ地図は上が西になっている。
| |
 |
|
東本願寺茨木別院を右に見て歩くと、右手に川立地蔵尊が祀られていた。
祠の中を覗くと、お化粧された女性?の地蔵さんが多数迎えてくれた。
つづく
| |
|
2月13日(木)06:19 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| No.19金剛山(狼尾根_紅葉谷第四堰堤) |
|
 |
|
この料理もたいてい注文する。
特選・得タネ盛合せ 880円(二人前相当)
この料理と先ほど注文した活真鯛あら煮を食べ終えるのに、かなり時間が掛かる。
つまり、ボリュームがあるということ。
| |
 |
|
店内の様子。
ふじの系列店らしく壁に“富士山”が描かれている。
| |
 |
|
貼り出しメニュー。
こちらの料理はいつもあるとは限らない。
串カツ盛合せ 6種 480円、リーズナブルだが、やはりこの店は海鮮モノがダントツに良いと思う。
| |
 |
|
松竹梅の豪快。
大阪の居酒屋では定番の日本酒という。
業務用向けで一般の顧客には販売していないようだ。
飲食店で楽しむ松竹梅
| |
 |
|
〆の巻き寿司。
これもお勧め。
海鮮巻 4個 380円也。
美味しかった御馳走様。
おしまい。
| |
|
2月12日(水)05:43 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| No.18金剛山(狼尾根_紅葉谷第四堰堤) |
|
 |
|
前方に葛城山を望みながら林道を歩く。
| |
 |
|
マメガキ
| |
 |
|
14時31分水越川公共駐車場に帰着。
| |
 |
|
この日の反省会は、今ではすっかりお馴染みとなったスタンド 富 阿倍野区阿倍野筋1-5-1 ルシアスビル B1F
阿倍野では比較的よく知られている「スタンド ふじ」の系列店で、場所はスタンド ふじ本店の斜め向いにある。
撮影した画像の右端に本店が少しだけ写っている。
| |
 |
|
この料理は私のお気に入り、活真鯛あら煮 280円。
この店に入ったら、たいてい注文する。
入店してすぐに注文するのが正解。
| |
|
2月12日(水)05:43 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| モーツァルト ピアノ協奏曲 第21番 |
|
|
モーツァルト ピアノ協奏曲 第21番を視聴してみよう。
Mozart Piano Concerto No 21
モーツァルト ピアノ協奏曲 第21番ハ長調 K 467 イングリット・ヘブラー Mozart Piano Concert No.21 C Major
モーツァルト: ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調 K.467 内田光子, テイト 1985
Mozart: Piano Concerto No. 21 - Netherlands Philharmonic Orchestra, Ronald Brautigam - Live HD
Mozart: Piano concerto n. No. 21 in C major, K.467 Pollini-Muti
| |
|
2月11日(火)20:40 | トラックバック(0) | コメント(0) | 音楽 | 管理
|
| No.17金剛山(狼尾根_紅葉谷第四堰堤) |
|
 |
|
紅葉谷右岸を下る。
| |
 |
|
この先、狼谷・狼尾根との分岐。
| |
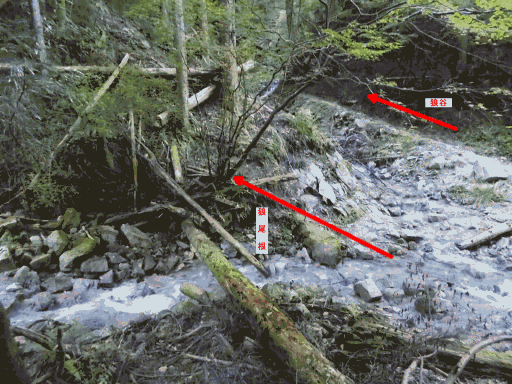 |
|
前方の踏み跡が狼谷への登山道。
今朝は二俣の間にある尾根(狼尾根)から登った。
| |
 |
|
登山者が作ったもの。
ごく最近だろう。面白い。
| |
 |
|
紅葉谷入渓地点に到着。
後はガンドガコバ林道をのんびりと歩く。
つづく。
| |
|
2月11日(火)06:16 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| No.16金剛山(狼尾根_紅葉谷第四堰堤) |
|
 |
|
紅葉谷第四堰堤左岸の上に出た。
登山道は右岸に付いているので渡渉することになる。
この後、上流(右)方向へ踏み跡を辿る。
| |
 |
|
樹木の幹に目印となるマーキングがされていた。
相当古いもので、かなり剥げている。
実は数ヶ月前にこの場所に立ったことがある。(2019年9月17日)
たった今、降りてきた踏み跡の取り付きを探索するのが目的だった。
しかし、その時は踏み跡を見つけることは出来ず。
なぜなら、まさか、ここから斜面(というより崖に見えてしまう)に向かって、直登するとは想定していなかった。
なのでトラバース道を探したが見つからず、踏み跡は消滅していると思い込んでしまった。
| |
 |
|
紅葉谷を右岸へ渡渉する。
| |
 |
|
何回か歩いている登山道に合流。
| |
 |
|
第四堰堤を後にして下る。
つづく。
| |
|
2月11日(火)06:16 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| モーツァルト ピアノ協奏曲 第19番 |
|
|
モーツァルト ピアノ協奏曲 第19番を視聴してみよう。
Mozart - Piano Concerto No. 19 (Hélène Grimaud)
Mozart - Piano Concerto No. 19 in F major, K. 459 (Mitsuko Uchida)
Mozart Piano Concerto no. 19 K459 in F major -- Haskil/Desarzens/OCL, 1957
MOZART Piano Concerto # 19 in F major ~ Maurizio Pollini / Böhm/ VPO
| |
|
2月10日(月)20:39 | トラックバック(0) | コメント(0) | 音楽 | 管理
|
| No.15金剛山(狼尾根_紅葉谷第四堰堤) |
|
 |
|
降りてきた踏み跡を振り返って撮影。
かなりの急斜面。
また、落ち葉が積もっていて滑りやすい。
| |
 |
|
この先、青テープを拾い、石の杭を左下に見て更に下る。
| |
 |
|
石の杭には「一〇」と彫られていたようだ。
| |
 |
|
真下に紅葉谷第四堰堤が見えるが、ここから先、下向するのが難しかった。
木の根っこなど、掴みどころがまったくなく、しかも落葉で滑りやすい。
ところが、この時点では気付かなかったが、この少し下からロープがあったので助かった。
撮影した画像ではわかりにくい。
右端の折れた木の幹からロープが垂れ下がっていた。
| |
 |
|
トラロープ。
傾斜がとても急で、ロープがなければ下向するのは危険だろう。
但し、登り道として利用するのは、それほど危険とは思えない。
つづく。
| |
|
2月10日(月)06:06 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| No.14金剛山(狼尾根_紅葉谷第四堰堤) |
|
 |
|
倒木に括りつけられた緑のテープを拾う。
| |
 |
|
更に赤色と黄色のテープを見る。
| |
 |
|
青色と赤色。
さながら信号機みたい―笑。
| |
 |
|
何かの動物の糞を発見。
鹿ではなさそう。
| |
 |
|
前方に堰堤らしき建造物が見える。
紅葉谷第四堰堤と思われた。
つづく。
| |
|
2月10日(月)06:06 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| No.13金剛山(狼尾根_紅葉谷第四堰堤) |
|
 |
|
ササで踏み跡が隠れている。
ストックでササを押し退けて下る。
| |
 |
|
緑のテープを拾いながら下る。
テープがあるので助かる。
| |
 |
|
この辺りの踏み跡は明確。
| |
 |
|
落ち葉が積もっており、滑らないよう注意しながら下る。
| |
 |
|
今度は黄色のテープ。
つづく。
| |
|
2月10日(月)06:04 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| No.12金剛山(狼尾根_紅葉谷第四堰堤) |
|
 |
|
目印のテープを拾いながら進む。
| |
 |
|
ササが生い茂り足元の登山道が見え難い。
| |
 |
|
眼下の紅葉谷の黄葉が美しい。
向こうに見える尾根はサネ尾だろうか、或いはダイトレの稜線かもしれない。
| |
 |
|
これまでトラバース気味に歩いていたが、この先、一気に下る。
| |
 |
|
ササが生い茂り踏み跡が分かりにくいが、テープを拾いながら慎重に下る。
つづく。
| |
|
2月9日(日)06:06 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| No.11金剛山(狼尾根_紅葉谷第四堰堤) |
|
 |
|
来た道と同じ狼尾根への踏み跡を途中まで辿る。
分岐付近はササが少し生い茂っているものの、歩く人が多いのか登山道は明白。
| |
 |
|
概略図が置かれた分岐に到着。
分かりにくいが直進が狼尾根。
左下への踏み跡を辿ると狼谷。
この日の下山道は紅葉谷第四堰堤へ向う。
ここからまずは狼谷分岐を左下に見送り狼尾根方面へ直進する。
| |
 |
|
概略図をもう一度確認する。
現在地から狼谷分岐を左に見送り、狼尾根方面へ直進。
| |
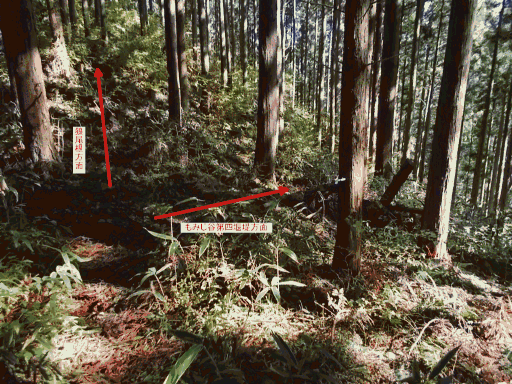 |
|
画像の分岐で左上(直進)の狼尾根方面を見送り、もみじ谷第四堰堤方面へ右折する。
| |
 |
|
もみじ谷第四堰堤方面への踏み跡を辿る。
これまでの登山道と較べ踏み跡が薄く、頻繁に歩かれていないことがわかる。
茨に注意。
つづく。
| |
|
2月9日(日)06:06 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| No.10金剛山(狼尾根_紅葉谷第四堰堤) |
|
 |
|
昼食場所から山頂広場の紅葉を眺める。
| |
 |
|
12時40分、山頂広場から下山を開始。
| |
 |
|
売店横のモミジともお別れ。
次週、再びここにやって来る頃には、黄葉は終わっているだろう。
| |
 |
|
売店横から大日岳方面へ向う。
| |
 |
|
この分岐で大日岳方面直進を見送り狼尾根方面へ右折する。
つづく。
| |
|
2月9日(日)06:05 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| No.9金剛山(狼尾根_紅葉谷第四堰堤) |
|
 |
|
歩き慣れた山頂広場方面への登山道を歩く。
| |
 |
|
売店横に出る。
左は転法輪寺方面、売店・山頂広場方面は右。
| |
 |
|
売店前モミジの黄葉。素晴らしい。
青空をバックに映える。
このモミジは紅葉ではなく“黄葉”。
この後、紅色に変わるとは思えない。
| |
 |
|
山頂の気温は7℃。
10℃を切っているので、普通だと暖房が欲しいところだが、体が火照っているので寒さを感じない。
しかし、昼食時など、じっとしていると寒い。
| |
 |
|
12時25分、いつもの国見城跡・山頂広場に到着。
日当たり場所を選んで昼食タイム。
つづく。
| |
|
2月8日(土)06:02 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| No.8金剛山(狼尾根_紅葉谷第四堰堤) |
|
 |
|
分岐地点に到着。
コースは左上へ進む。
右は狼谷への下山道。
| |
 |
|
分岐に置かれた概略図。
狼尾根を歩いてここへ来た。
大日岳・山頂広場方面へ向う。
| |
 |
|
狼谷の源頭部を登り詰める。
| |
 |
|
前方に稜線が見えてくると大日岳と山頂広場方面との分岐地点が近い。
| |
 |
|
分岐地点に到着。
ここは三叉路になっている。
大日岳方面を右に見送り、山頂広場方面へ左折。
つづく。
| |
|
2月8日(土)06:01 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|