| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山65 |
|
 |
|
この先、舗装道路に出合う。
見覚えのある分岐。
| |
 |
|
分岐を左に歩くと、朝、歩いた住吉川に架かる東谷橋に到着。
朝、この橋を渡って行った。
| |
 |
|
分岐に戻る。
コースは直進。
| |
 |
|
分岐からは往路とほとんど同じ道を歩いて阪急御影駅へ向かった。
なので、撮影した画像は少い。
| |
 |
|
行きには気づかなかった水車小屋跡の説明板。
水車小屋跡
住吉川には、すでに17世紀はじめ小規模な水車が築けられ、菜種や綿種の油を絞るのに利用されていた。
その後、精米や製粉にも利用され、特に酒米精製に不可欠となった。
明治末から大正中期の全盛期には80余棟の水車場が軒を並べていたが、今では谷あいに跡を残すのみとなっている。
東灘区役所
| |
|
10月7日(日)17:16 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 近松門左衛門ゆかりの地2 |
|
 |
|
近松門左衛門の墓入口。
この左奥に墓があるが、この日は多人数で訪れていることもあってお参りせず。
| |
 |
|
国指定史跡 近松門左衛門墓
近松門左衛門は、享保九年(一七二四)に七二歳で没した。
近世で最も著名な劇作家の一人である。
近松は、竹本義太夫や二代目義太夫のために百作を越える浄瑠璃を著す一方で、坂田藤十郎のために三十数作の歌舞伎狂言を著している。
「曾根崎心中」「心中天網島」「女殺油地獄」などの世話物に代表される作品に描かれる人間の姿は、今日に通じるところも多く、伝統芸能や演劇・映画などの中で再創造され、たくさんの人々に感動を与え続けている。
近松門左衛門墓は、当初近くの法妙寺(現在大東市へ移転)境内にあったが、昭和五五年(一九八○)財団法人住吉名勝保存会はじめ市民の方々の協力を得て、当地に移転し、整備が図られた。
平成七年十月二十八日 大阪市教育委員会
| |
 |
|
小春・治兵衛の比翼塚と鯉塚
享保5年(1720)10月14日、天満の紙屋の主人治兵衛と曾根崎新地の遊女小春が大長寺で心中しました。
近松門左衛門がさっそくこれを浄瑠璃にしたてたのが名作「心中天網島(しんじゅうてんのあみじま)」で、人々が2人をあわれんで建てたのがこの比翼塚です。
大長寺はもと網島(現在の藤田美術館敷地内)にありましたが、明治42年いまの場所に移転し、それとともに塚も移されました。
比翼塚のとなりに鯉塚があります。
寛文8年(1668)淀川でとれた巴の紋のついた大きな鯉に「滝登鯉山居士」の法名を与え葬ったものと伝えられています。
おしまい。
| |
|
10月6日(土)18:05 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理
|
| 近松門左衛門ゆかりの地1 |
|
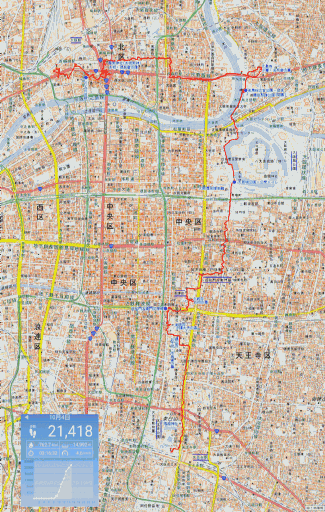 |
|
2018年10月4日(木)はJRのふれあいハイキングに単独で参加した。
タイトルは「近松門左衛門のゆかりの地を訪ねて」。
<概要>
主催は近畿ウォーキング笑会。略して“近笑会”。
この会には初めて参加した。
「あんたの大阪50キロウォーク」「近笑会100キロウォーク」など長距離のウォークも催されており、参加者の中には健脚の人が多いという印象。
平日の開催ということもあり、この日参加されたのはリタイヤされたとみられる高齢者が大半。
スタートは天王寺駅、ゴールは大阪駅。
大阪市内に点在する近松門左衛門ゆかりの地と文学碑を訪問。
過去に近松門左衛門の墓所を訪れたことがあるが、立ち寄った程度で、近松門左衛門のテーマで歩いたのはこれが初めて。
ウォーキング団体主催のイベントで、多人数参加(目測80名程度)しており、例によって訪問したポイントでの説明はなく、淡々と歩くのみ。
天気予報では曇り一時雨(15:00~)とのことだったが、イベント開催時間中は(9:30頃から13:30頃)継続的に小雨が降っていた。
一時的に傘を差さなければどうしょうもない程、降った時もあり、最後まで傘は仕舞えず。
【参考】
・近松門左衛門は江戸時代前期の浄瑠璃、歌舞伎狂言の作者で「心中宵庚申」(しんじゅうよいごうしん)「夕霧阿波鳴渡」(ゆうぎりあわのなると)「心中天網島」(しんじゅうてんのあみじま)「曾根崎心中」(そねざきしんじゅう)等が有名。
・銀山寺 お千代 半兵衛の墓
・夕霧太夫の眠る 淨國寺
・近松門左衛門文学碑
・お初の墓
・近松門左衛門の墓
・大長寺 小春・治兵衛の墓
・お初・徳兵衛の像
・しじみ川旧跡
・近笑会100キロウオーク参加募集
<コース>
JR天王寺駅_9:20【集合】天王寺公園てんしば9:40_<谷町筋>_日本パブテスト大阪教会前_堀越神社前_四天王寺南(交差点)_大阪星光学院前_真光院前_地下鉄四天王寺前夕陽ヶ丘駅出入口_銀山寺前(お千代・半兵衛の墓)_<源聖寺坂>_<松屋町筋>_浄國寺(夕陽太夫の墓)_下寺町歩道橋を渡る_近松門左衛門文学碑_久成寺(くじょうじ)(お初の墓)_高津公園_高津宮(神社)前_近松門左衛門の墓前_楠木大神前_上本町4(交差点)_<上町筋>_難波宮跡公園前_大阪歴史博物館前_ローソン S大手前レストハウス店前_大阪城公園・公衆トイレ_11:41毛馬桜之宮公園・藤田邸跡公園(倒木により当分の間閉園)前・昼食12:10_大長寺(だいちょうじ)(小春・治兵衛の墓)_<曾根崎通>_大川に架かる新桜宮橋を渡る_桜之宮公園(泉布観)前_近鉄バス 桜の宮橋バス停前_JR東西線大阪天満宮駅・地下鉄堺筋線南森町出入口前_堀川小学校前_<天神橋筋>_堀川戎神社前_妙香院前_満マル 東梅田店前_露天神社(つゆのてんじんじゃ 別名:お初天神)(お初・徳兵衛の像)_しじみ川旧跡_13:25JR大阪駅
<その他>
・参加者目測80名程度。
・リーダーS氏。
・コース歩行距離約13km。
・実歩行距離約15km。(自宅~最寄り駅往復約2.7km等を含む)
・歩数2万1千歩。
画像は天王寺駅から大阪駅までのGPSログを表示。
※大阪駅周辺は高層ビル群によりGPSの受信状態が悪く正しく表示されず。
| |
 |
|
源聖寺坂を下る。
源聖寺坂
この坂は、登り口に源聖寺があるので、その名をとっている。付近一帯は、寺町として長い歴史を持つ。
齢延寺には、幕末に泊園書院を興して活躍した藤沢東畡、同南岳父小の墓があり、銀山寺には、近松門左衛門の「心中宵庚申」(しんじゅうよいごうしん)にでてくる<お千代、半兵衛>の比翼塚が建てられている。
| |
 |
|
近松門左衛門文学碑。
千日前通と松屋町筋が交差する下寺田町交差点北西角に建つ。
(スーパー玉出 日本橋店の南)
| |
 |
|
「(曾根崎心中) お初の墓」は真ん中の墓ですと、指差すリーダーの人。
ところが、後で調べるとそうではなく、一番右の小さい墓碑がそれだった。
久成寺(くじょうじ)にて。
| |
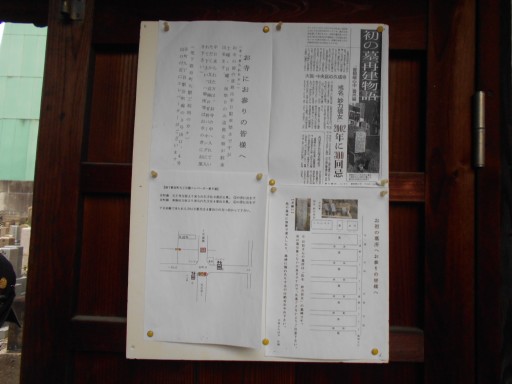 |
|
久成寺の山門に掲げられていた「お初の墓」。
墓碑には「法名 妙力信女」と刻まれている。
平成十四年、お初の三百回忌に当り住職が再建。
| |
|
10月6日(土)18:05 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理
|
| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山64 |
|
 |
|
石段を降りる。
左下に住吉川の流れる音が聞こえる。
| |
 |
|
登山道は少々荒れているので注意して下る。
| |
 |
|
住吉台の住宅地が出来るまでこちらの道が古くから歩かれていたのだろう。
| |
 |
|
整然と積まれた石段を降りる。
| |
 |
|
傾斜が緩やかになり歩きやすくなる。
| |
|
10月5日(金)18:52 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山63 |
|
 |
|
小さな橋から右方向(西)を眺める。
道路が見えるが、この上は住吉霊園とみられる。
| |
 |
|
3級基準点(点名:1013 六甲砂防事務所)が地面に埋め込んであった。
| |
 |
|
右側に擁壁が続く。
左下は住吉川の流れ。
| |
 |
|
この先、道標が立つ分岐。
| |
 |
|
矢印の赤マークを見て左へ下る。
左下は「住吉3.3km 御影2.6km 住吉道」と表示されている。
直進は「住吉台」。これは住宅地。
ゴールはスタートと同じ阪急御影駅。
| |
|
10月5日(金)18:49 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山62 |
|
 |
|
分岐に立つ道標。
住吉道・六甲最高峰方面からここへ来た。
下山は白鶴美術館・住吉駅方面へ向かう。
| |
 |
|
分岐を振り返って撮影。
| |
 |
|
幅広の歩きよい道を歩く。
| |
 |
|
広場のようなところに出る。
植林されているようだ。
| |
 |
|
この先、小さい橋を渡る。
| |
|
10月5日(金)18:44 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山61 |
|
 |
|
「馬食わず」。
有毒の蔓性植物。仙人のひげに見立てたことから「センニンソウ」の別名?正式名?がある。
| |
 |
|
五助谷の眺め。
下山した気分だが、まだまだ山の中。
| |
 |
|
荒れた道を歩く。
舗装が剥れている。
| |
 |
|
見覚えのある場所、石切道登山口に到着。
朝、左の道からここへ来て、右上に続く石切道を歩いた。
下山は正面の道を歩く。
この分岐では、四方向に伸びるすべての道を歩いたことになる。
| |
 |
|
朝、ここから石切道を歩き始めた。
ここが石切道登山口。
| |
|
10月4日(木)19:00 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山60 |
|
 |
|
五助堰堤(五助砂防ダム)を左に見て歩く。
| |
 |
|
当然ながら堰堤へは立入禁止。
| |
 |
|
石段を下る。
| |
 |
|
あちこちにベンチが置かれている。
| |
 |
|
「六甲山の生い立ちと地形の変化」。
国土交通省六甲砂防事務所が立てた説明板。
| |
|
10月4日(木)18:56 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山59 |
|
 |
|
木道を歩く。
辺りは湿地になっている。
| |
 |
|
少し登り返す。
| |
 |
|
住吉川の流れ。
| |
 |
|
歩いて来た方向を振り返って撮影。
| |
 |
|
擁壁の上に造られた道を歩く。
| |
|
10月4日(木)18:53 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山58 |
|
 |
|
下草が生い茂った河原を歩く。
| |
 |
|
住吉川に出合う。
前方に登山者の姿が見えた。
住吉川沿いに下って来たようだ。
| |
 |
|
登山者(右)と挨拶を交わす。
上流方向にも登山者の姿が見える。
少し上流方向を様子見する。
| |
 |
|
住吉川に架かる木の橋が流されていた。
| |
 |
|
住吉川の右岸に沿って下る。
| |
|
10月3日(水)18:25 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山57 |
|
 |
|
赤テープを拾いながら進む。
| |
 |
|
沢の中をジャブジャブ歩く。
| |
 |
|
矢印の赤マークを見て、沢から抜け出す。
| |
 |
|
住吉川の河原に出たようだ。
| |
 |
|
周りを見渡すと、あちこちで土砂崩れが起きていた。
| |
|
10月3日(水)18:21 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山56 |
|
 |
|
再び歩き出す。
ここからこの日一番の藪コギとなる。
| |
 |
|
かがんで、ヨチヨチ歩きのようにして進む。
地面近くの方が、意外とブッシュが少ない。
| |
 |
|
ようやくブッシュから抜け出し、谷の源流へ降りる。
| |
 |
|
石ころが多く、浮石もあってスムーズに進めない。
転倒に注意。
| |
 |
|
そろりそろりと歩く。
ここは落石に注意。
こんな足場の悪いところが、本来のルートとは思えない。
崩落地点を迂回する臨時のルートだろう。
| |
|
10月3日(水)18:18 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| ミドリ・ザイラー |
|
|
ミドリ・ザイラーを聴いてみよう。
(古楽演奏と現代舞踏の融合)
(HD) Vivaldi: Le quattro stagioni | Midori Seiler & Akademie für Alte Musik Berlin
| |
|
10月2日(火)20:16 | トラックバック(0) | コメント(0) | 音楽 | 管理
|
| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山55 |
|
 |
|
右側の眺望が開けるが、曇っており視界が悪い。
| |
 |
|
前を歩く登山者が、この先、登山道が崩壊と声を発した。
| |
 |
|
出発時点でリーダーから聞いていた崩壊地点に遭遇。
| |
 |
|
ここは左に迂回する。
人の歩いた跡と矢印の赤マークを見ながら下る。
| |
 |
|
この先、ブッシュ。
ここは危険で迷いやすい所なので、後続の人たちに知らせるべく小休止。
| |
|
10月1日(月)18:25 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 住吉川左岸_石切道_凌雲台_五助山54 |
|
 |
|
下草が生い茂った登山道を谷の方に向かって大きく下る。
| |
 |
|
矢印の赤マークがなければ迷うところ。
| |
 |
|
支尾根を歩く。
一転してこのあたりは下草がまったく見られない。
| |
 |
|
腰の高さくらいまで茂ったササを掻き分けて進む。
| |
 |
|
登山道の右側は樹木が生えておらず明るい。
| |
|
10月1日(月)18:20 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|