| 杵築神社_十三峠_水呑地蔵尊_心合寺山古墳 |
|
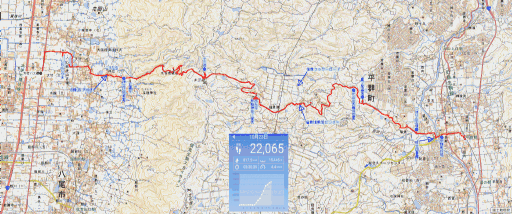 |
|
2018年10月23日(火)は、土曜会の有志で、生駒近辺の山や峠越えの道を歩くシリーズの第三回 「平群駅から十三峠へ」に参加した。
<概要>
スタートは近鉄生駒線平群(へぐり)駅。
奈良県側から十三峠越えを歩いて生駒山地を大阪側へ横断。
ゴールは近鉄バス大竹バス停。
十三峠越は、二ヶ月前の8月12日に、おおばこの会、「業平道パートⅢ~竜田川から十三越え~」で歩いている。
今回歩いたのは、業平道より、一つ北側に位置する車道を歩いた。
朝の天気予報では、曇り正午過ぎに小雨だった。
ところが、予報に反して、平群駅では雨脚が強く、出発を遅らせることに。
駅近くにある平群町役場に立ち寄って、ハイキングマップなどを入手し時間を稼いだが雨は止まず。
傘を差してのスタートとなった。
コース途中にある、つぼり山古墳に立ち寄り、重文 藤田家へ。
ここは個人の住宅で、一般公開はされていない。
雨の中、石仏が祀られている覆屋付近の掃除をされていた地元の人の話では、来る11月3日に特別公開されるという。(要予約)
その後、コースの途中にあり眺望が得られる星ノ尾墓地の東屋で雨宿りをするも、雨は一向に収まらず。
杵築(きづき)神社に立ち寄り、境内の軒の下を借りて昼食。
食後は十三峠へひたすら舗装道路を歩く。
時々、クルマが通行。
十三峠では十三塚に立ち寄り、十三街道ハイキング道を下った。
水呑地蔵尊で小休止。
ここからは大阪平野の眺望が得られるが、生憎の天気で霞んでおり、霧がかかったような状態。
十三街道ハイキング道には、二体の石仏が置かれている。
通説では、三十三番から一番まで合計六十六体あるとされるが、失われた石仏も多いようだ。
これらの石仏群は神立(こうだち)辻地蔵堂まで続く。
心合寺山(しおんじやま)古墳には、「八尾市立しおんじやま古墳学習館」があり、見学の予定だった。
ところが、この日(火曜日)が生憎の休館日で、古墳の中にも立ち入ることが出来なかった。
東高野街道に沿って走っている大竹バス停から近鉄バスに乗って終点瓢箪山駅で下車。
餃子の王将 瓢箪山店で反省会。
<コース概略>
近鉄生駒線平群駅_平群町役場_つぼり山古墳_杵築(きづき)神社・昼食_十三峠・十三塚_心合寺山(しおんじやま)古墳_大竹バス停_<近鉄バス>_近鉄奈良線瓢箪山駅 反省会:餃子の王将 瓢箪山店
<コース詳細>
9:20近鉄生駒線平群(へぐり)駅9:28_竜田川遊歩道案内図_平群ハイキングマップ_平群町役場(ハイキングマップ入手・雨宿り)_道標(十三峠・十三塚4.6km 藤田家住宅1.2km つぼり山古墳400m)_竜田川に架かる平群橋を渡る_覆屋(地蔵菩薩像)・記念碑(郡山高校平群分校記念碑)_福貴大字案内図_道標(→つぼり山古墳0.3km)_中央公民館前バス停前_道標(つぼり山古墳0.3km 重文 藤田家0.6km)_説明板(県指定史跡 ツボリ山古墳)_分岐道標(→楢本神社0.8kmを右に見送り ←重文藤田家0.3kmへ直進)_分岐・福貴案内図・道標(普門院0.4km)_説明板(重文 藤田家住宅)_覆屋(石仏群)_星ノ尾墓地(雨宿り)_新羅王子孫 光山金氏専用霊園前_水道施設前_覆屋(石仏群)_分岐道標(←十三峠2.3km 平群駅3.1km)_福貴畑集落センター前_覆屋(石仏群)_信貴フラワーロードを横断_道標(→杵築神社0.8km 平群駅3.4km←)_西光寺_覆屋(一観音六地蔵石仏 永禄十一年)_11:40杵築(きづき)神社・昼食12:18_墓地前_信貴生駒スカイラインの高架下を潜る_十三峠・生駒縦走歩道出合い_説明板(生駒十三峠の十三塚)_石柱(十三塚)_十三峠_道標(服部川駅→)_<十三街道ハイキング道>_ハイキングマップ(府民の森 みずのみ園地 →水呑地蔵尊0.3km 服部川駅3.5km)_水呑地蔵尊_通行止の看板_丁石(八丁)_神立(こうだち)園地分岐を左に見送り直進_祠(野仏)_二体石仏群(通説:三十三番から一番まで合計六十六体)_丁石(四丁)_路肩崩壊・注意して通行_神立茶屋辻・歌碑(君来むと いひし夜ごとに過ぎぬれば 頼まぬものヽ恋ひつヽぞ経る / (訳)あなたが「君に逢いに行くよ」と言ったから、私は毎夜あなたが来るを待っているけれど、いつもあなたは来ないままむなしく過ぎてしまう。だから、あなたの訪れをあてにはしていないけれど、でもあなたを恋しいと思いながら、わたしは過ごしているのです)_石柱(史跡の道 八尾市)・石碑(神立茶屋辻 この街道はむかし大阪玉造と大和竜田を結ぶ重要な道筋にあたりこの辻には多くの茶屋が並んでいたのでその名がある。また在原業平と茶屋娘の恋物語りで名高い。業平が峠を越え玉祖神社へ参詣の途中、福屋の娘梅野をみそめたが、ある夜東窓があいていたので中をのぞくと、娘が手づからでめしを食っているので、急に興ざめ逃げ帰った、娘は後を追ったが見あたらず悲んで渕に身を投げた。この高安の里では、今でも東窓を忌み、これをあけると娘の縁が遠くなるという伝説がある。この道を登ると水呑地蔵、十三峠がある。八尾市教育委員会)_正福寺前_神立辻地蔵堂_覆屋(石仏四体)_道標(右 大坂道 / 左 信貴山 米尾山江三十六丁 た川多(つた) 法里遊右(りゆう)じ 大和ミち 十三越 / 安政×二年九月世話人×)・道標(→神立墓地 愛宕塚 心合寺山古墳)_説明板(向山古墳と向山瓦窯跡)_清水園前(イチゴ直売所)_道標(→心合寺山古墳)_大竹会館前バス停前_心合寺山(しおんじやま)古墳_八尾市立しおんじやま古墳学習館前_14:13大竹バス停14:15_<近鉄バス>_近鉄奈良線瓢箪山駅 反省会:餃子の王将 瓢箪山店
<その他>
・参加者総勢3名。
・実歩行距離約15km。(自宅~最寄り駅往復約2.7km等を含む)
・歩数2万2千歩。
・反省会 餃子の王将 瓢箪山店
画像はこの日歩いた近鉄生駒線平群駅から近鉄バス大竹バス停までのGPSログを表示。
| |
 |
|
一観音六地蔵。
資料によると、永禄十一年六月廿四日の銘。
杵築神社参道石段脇にて。
| |
 |
|
(左)深沙大将立像。(じんじゃだいしょうりゅうぞう)
資料によると、玄奘(三蔵法師)が仏教の根本を求めて唐よりインドへ向かう途中、砂漠で遭難しかかった所を助けた神。
県指定文化財。室町時代後期作。
(中)聖観音坐像。
桧の寄木造。
天文十七年八月十八日 空阿 宿院仏師源次。
町指定文化財。
杵築神社、観音堂に安置。
| |
 |
|
神立(こうだち)辻地蔵堂。
ここから十三峠に向かって、二体の石仏が置かれている。
通説では三十三番から一番まで合計六十六体あるとされるが、失われた石仏も多いようだ。
| |
 |
|
十三峠越えに立つ道標。
「右 大坂道 / 左 信貴山 米尾山江三十六丁 た川(つ)多(た) 法里(り)遊(ゆ)右(う)じ 大和ミち 十三越 / 安政×二年九月世話人×」。
八尾市神立六丁目にて。
おしまい。
| |
|
10月26日(金)17:50 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理
|