| 灘の酒蔵巡り8 |
|
 |
|
2階へ登る。「ひねり餅の型」。
ひねり餅とは、清酒の醸造過程で原料米の蒸し加減をみるために、その一部をとり、手でひねりつぶし餅状にしたもの。
画像はその型。
| |
 |
|
樽廻船(たるかいせん)。
江戸時代、灘で造られたお酒を、大坂、西宮あたりから江戸へ輸送するために用いられた廻船(貨物船)。
| |
 |
|
このようにして樽酒を運んでいた。よく作られた模型。
沢の鶴は、元は両替を主に扱う商人であり、大名の蔵屋敷に出入りし、藩米を取り扱う仕事を主に行っていた。当時の屋号は米屋。その別家の米屋喜兵衛が米屋のほか、副業で酒を造り始めたことがはじまり。酒樽に見られる商標が※印なのはそのため。現在、この商標は使われていない。
沢の鶴 - Wikipedia
| |
 |
|
昭和初期頃のポスター。
| |
 |
|
資料館の見学はこれくらいにして、試飲や買い物が出来るミュージアムショップへ行く。
| |
|
7月14日(木)20:48 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理
|
| 灘の酒蔵巡り7 |
|
 |
|
「醪(もろみ)仕込」コーナーに置かれていた大桶(おおおけ)。
灘の三段仕込(初・中・留)の工程で使用されていた大小様々な仕込用桶の一つ。
| |
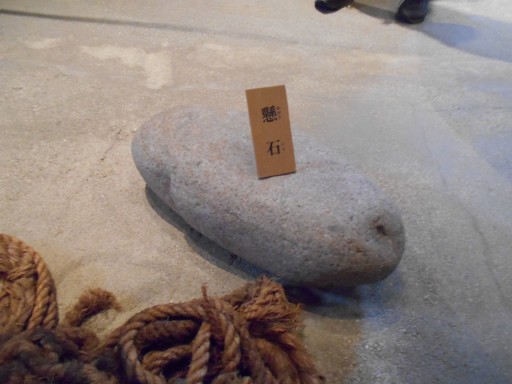 |
|
「上槽(じょうそう)」コーナーに置かれていた懸石(かかるいし)。
上槽(じょうそう)とは、醪(もろみ)を搾ってお酒と酒粕に分離する工程。
揆(はね)つるべと同じく、懸石は石の重みを利用したテコの原理で重しとして使用していた。
| |
 |
|
酒や水を天秤棒でかついで運ぶ担い桶(にないおけ)。
上に吊るしてあるのは渋袋(しぶくろ)。
| |
 |
|
いろいろな杓(しゃく)。
| |
 |
|
草履(ぞうり)さし。頭や杜氏が履く草履は色が付いている。
それにしても役割が細かく分かれている。
| |
|
7月14日(木)20:47 | トラックバック(0) | コメント(0) | ウォーキング・散策 | 管理
|