| 星田山_日高山_森の宝島34 |
|
 |
|
「清滝スポーツ・ヒルズ」前を通過。
この施設は「学校法人天満学園」が運営している。
| |
 |
|
お馴染みの緑の文化園、駐車場に到着。
駐車場の中を通り抜ける。
| |
 |
|
水辺自然園入口ゲートを潜る。
※水辺自然園には行かない。
| |
 |
|
森の工作館前を通過。
| |
 |
|
緑の文化園の中に入っているが、舗装道路になっている。
残念だがこれでは森を散策した気分にはなれない。
| |
|
9月9日(土)20:13 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 星田山_日高山_森の宝島33 |
|
 |
|
「森の宝島」を後にする。
| |
 |
|
道標を見て「むろいけ園地水辺自然園方面」へ向かう。
| |
 |
|
古道の趣きがある道を少しだけ歩く。
この先分岐。右方向は登山道が崩落しているのか通行止と
なっていた。
| |
 |
|
ほどなく車道に出合い右折。
| |
 |
|
暫く歩道を歩く。
| |
|
9月8日(金)20:04 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 星田山_日高山_森の宝島32 |
|
 |
|
駐車場の中を通り抜ける。
| |
 |
|
日陰のベンチを見つけ、ここで昼食タイム。
| |
 |
|
先頭グループは11時40分に到着、12時10分に出発予定のメモ。
| |
 |
|
食事を終え、12時35分出発する。
| |
 |
|
トイレ横の階段を登る。
ここから暫くの区間は初めて歩く。
子供向けの遊具場のある「森の宝島」へ立ち寄ることはないので。
| |
|
9月8日(金)19:59 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 星田山_日高山_森の宝島31 |
|
 |
|
旧清滝街道を右(西方向)に見送る。
| |
 |
|
引き続き車道に併設された歩道を暫く歩く。
| |
 |
|
11時47分、「緑の文化園 むろいけ園地 森の宝島」入口に到着。
ルートはこの分岐を右折するが、ここでH氏の到着を待つ。
| |
 |
|
「森の宝島」という名前は、子供が楽しめる遊具場ほどの意味。
具体的には、わいわい広場、花かごの谷、梅林、森の劇場などの施設がある。
| |
 |
|
暫くしてH氏が到着。ここで昼食。
時間は12時過ぎ。
| |
|
9月8日(金)19:54 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 星田山_日高山_森の宝島30 |
|
 |
|
分岐に立つ案内板。
四條畷市歴史散策道
清滝街道の今昔
本市の中央部を東西に貫く古道は、清滝街道と呼ばれ、多くの人びとに利用されてきた。 蔀屋(しとみや)西端から東へ山間を越えて下田原に至り、磐船街道と交又する約7kmのこの道は、古代より河内と大和を結ぶ重要な道であった。
戦後は国道163号として整備され、平成2年には清滝トンネルが開通し、急坂が解消されて、いよいよその重要度が増している。
数字を付して西から古道をたどると、①は本市で最も古い道標で「これより東清滝」と刻まれ、延宝3(1675)年に建てられている。②蔀屋浜は寝屋川舟運の要地であった。道は清滝川北岸沿いに外環状線を横断、体育館を左に東進する。③雁塔・西征戦死招魂碑の前を過ぎ、JR片町線の踏切を過ぎると、④中野派出所前。ここは明治7年に中野屯所が設置された所。児童公園は旧役場跡地で、このあたり約100mは東高野街道と重なる。⑤道標を過ぎ東進すると、左の高台は⑥白鳳時代創建の旧正宝寺跡。清滝川の北岸をたどり⑦国中神社の鳥居をくぐり約800m登ると163号と交又する。ここから先は国道改修工事により姿を変えているが、一部は山間の古道の姿を残している。⑧水道局ポンプ場からは古道が整備され、登りつめた右側には⑨府指定文化財の五輪塔がある。
峠から東は街道と国道がつかずはなれず下田原へと続き、集落の入口で分かれて東に進む。⑩天満宮、⑪珍しい墓塔型の道標を見つつ東に進み⑫前川橋を渡る。北200mには⑬耳なし地蔵を祀る法元寺。南200mには⑭照涌井戸。道は川沿いに進み高橋を渡り、磐船街道と交わる。橋の手前には⑮大正八年建立の府県境標石がある。
四條畷市教育委員会
| |
 |
|
ここにも地元四條畷市と四條畷中学校が立てた駒札。
のぼりつめ
清滝峠の
茶屋の跡
貝原益軒は「清滝嶺の茶屋一あり、是大坂越の嶺なり」と、元禄の昔に語られた茶屋一字は、江戸末期まで存在したらしい。
| |
 |
|
逢阪五輪塔。
一見すると損傷もなく江戸時代くらいの建立かと思ったが、延元四年(1336年)で、今から681年前の南北朝時代のもの。
| |
 |
|
延元の
年月きざむや
逢阪の五輪塔
基部から、地・水・火・風・空輪と呼ばれる。地輪部中央に「大坂一結衆延元元丙子三月日造立之」の銘がある。府指定有形文化財。
| |
 |
|
逢阪 石造五輪塔
(大阪府指定文化財・高さ約2m)
この五輪塔は、上の方から空・風・火・水・地の5つの部分からなり、密教思想を伝える鎌倉時代の様式をあらわしています。
塔には建立の年も刻まれ、四條畷市で最も古く、大きさも立派なものです。
<逢阪千軒>といわれ賑わったこの地にふさわしい文化財といえるものです。
(地輪に刻まれた文字)
大坂一結衆(大坂は逢阪のこと)
延元元丙子三月 日(1336年)
造立之
| |
|
9月7日(木)20:18 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 星田山_日高山_森の宝島29 |
|
 |
|
車道沿いに歩くが、アスファルトの照り返しもあって異常に暑い。
見所もないのでピッチを上げて早足で歩く。
| |
 |
|
車道を右に渡る。
| |
 |
|
信号機のある三叉路の交差点を直進。
| |
 |
|
すると右側に「大東・四條畷ハイキングコース案内」が立っている。
塗装を塗り直したのか綺麗に描かれている。
現在地から「逢阪の五重塔」を観て「緑の文化園」へ入りここで昼食。
食後は府民の森駐車場を通って蟹ヶ坂ハイキングコースを歩く。
御机神社前、四條畷神社前、四條畷学園前を通ってJR片町線四条畷駅へゴールする。
| |
 |
|
民家の前を通り過ぎると分岐。
コースは右方向の旧道(清滝街道)を見送り直進。
| |
|
9月7日(木)20:14 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 星田山_日高山_森の宝島28 |
|
 |
|
役行者像が彫られている石は左右の巨岩とは異なっているように見える。
像の後、灰色に見えるのは鉄板なのか石なのかよくわからない。
| |
 |
|
傍らに祀られていた石仏群。
中央の石仏は阿弥陀如来坐像だろう。
| |
 |
|
おそらく旧道沿いに点在していた石仏たちをこの一ヶ所に集めたと見られる。
| |
 |
|
箱型双石仏。
向かって左、地蔵立像。右は阿弥陀如来立像だろう。
| |
 |
|
車道に出合い左折。
逢阪(おおさか)バス停前を通過。
車道に併設された歩道を暫く歩く。
| |
|
9月7日(木)20:07 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 星田山_日高山_森の宝島27 |
|
 |
|
この民家にも蔵が見られる。
| |
 |
|
分岐。
前方に見える車道を左に行くので、この分岐はどちらを歩いても同じ。
| |
 |
|
稲の実がもう生っていたので少し驚いた。
| |
 |
|
地元四條畷市と四條畷中学校が立てた駒札。
幸多かれと 原始の祈り 巨石につた茂る
三メートルほどの巨石が双立する巨石信仰。真中に役行者の石像が祀られている。境域には数多くの仏たちが建ち並び地元逢阪の聖地である。
| |
 |
|
巨石の間に役行者像をはめ込み、その上に笠石らしき石を乗せている。
| |
|
9月6日(水)19:56 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 星田山_日高山_森の宝島26 |
|
 |
|
道端に参加者のものと思われる扇子が落ちていたので、拾ってTリーダーに預けた。
| |
 |
|
讃良川(さらがわ)に架かる橋を渡る。
| |
 |
|
クサギの花。
| |
 |
|
前方に四條畷市逢阪(おおさか)の集落が見えてくる。
| |
 |
|
蔵持ちの立派な旧家が建ち並ぶ。
| |
|
9月6日(水)19:52 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 星田山_日高山_森の宝島25 |
|
 |
|
正面に見えるピークは拂底山258.7m。(ぼってやま)
この日のコースでは、この山には登らず。
拂底山は市境に位置し北側は交野市星田、南側は四條畷市岡山。
四條畷市側から撮影している。
| |
 |
|
刈り取った下草を野焼きしていた。
| |
 |
|
未舗装の林道を歩く。
日陰がなく暑い。
| |
 |
|
暑い中、畑の手入れをされていた。
| |
 |
|
炎天下の中、林道歩きが続く。
| |
|
9月6日(水)19:49 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 星田山_日高山_森の宝島24 |
|
 |
|
前方に鉄製の柵が現れる。
ここまで歩いて来た林道の入口で、車両通行止の柵と見られる。
柵の左にガードレールが見える。
このあたりから、藁を焼くような、懐かしい田舎の匂いがしてきた。
| |
 |
|
ガードレールを跨いで、矢印の通り左折。
| |
 |
|
その先は、両脇にガードレールが設置され、道路は簡易舗装されているが雑草が生い茂っている。
| |
 |
|
ガードレールを跨いだところを振り返って撮影。
| |
 |
|
簡易舗装道路を歩く。
前方で野焼きが行われていた。
藁を焼くような匂いの正体はこれ。
| |
|
9月5日(火)20:08 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 星田山_日高山_森の宝島23 |
|
 |
|
山頂は展望もないので、休憩せずにそのまま通過する。
山頂からは緩やかに下る。
| |
 |
|
高低差のほとんどない穏やかな尾根道を暫く歩くと分岐となる。
尾根筋をそのまま進めば「国見嶺」と呼ばれるピークに辿り着くが、この日のコースはここで左折。
| |
 |
|
その先も高低差はほとんどなく平地を歩くイメージ。
| |
 |
|
葛が周囲の潅木を覆っている。
下草が生い茂っているものの、踏み跡は比較的明確。
| |
 |
|
この先、坂道が続く。
穏やかに下る。
| |
|
9月5日(火)20:04 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 星田山_日高山_森の宝島22 |
|
 |
|
右側には「右(東) 星田山 ボッテ谷」と記入。
ところがこれから向かう日高山の案内表示がなかったように思う。
| |
 |
|
分岐に立つ道標を振り返って撮影。
画像の左方向が「坂登山 星田山手」。
右方向が「星田山 ボッテ谷」でこの方向からここへ来た。
この後、南方向へ歩く。
| |
 |
|
やや薄暗い急坂の小道を登り詰める。
| |
 |
|
平坦な尾根筋に出る。
| |
 |
|
そのまま尾根筋を歩くと、暫くして日高山の山名板が目に留まった。
うっかりすると通り過ぎてしまう。
私製の道標には標高260mと記入。
| |
|
9月5日(火)19:59 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 越ヶ滝_三合目_岩湧山_滝畑ダム |
|
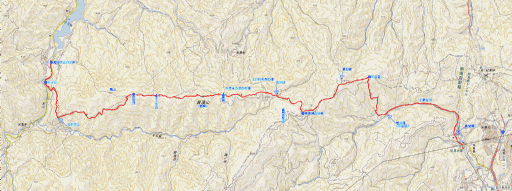 |
|
2017年9月3日(日)は山を登る会の第962回例会に単独で参加した。
山域は和泉山脈。
南海電鉄高野線紀見峠駅から、根古川に沿って歩き、越ヶ滝を経て岩湧山三合目650mへ。
以後はダイトレに合流し、根古峰749.4m分岐、南葛城山分岐を経て五ツ辻754mへ。
岩湧山897.7mで昼食。
下山はキトラ山790m、カキザコを経て滝畑ダムバス停。
バス停から南海バスで河内長野駅へゴールした。
歩行距離約12km。リーダーはN氏。
参加者76名。
コース
南海高野線紀見峠駅9:40_南海高野線天見3号踏切を横断_道標(→岩湧山 三石山)_養叟庵前_道標(←岩湧山)_案内板(根古川)_植林伐採地_越ヶ滝展望台前_分岐(→岩湧山)・休憩_送電線鉄塔_分岐を左へ_岩湧山三合目650m・ダイトレに合流・休憩_ダイトレから離れ脇道を歩く_ダイトレに合流_根古峰749.4m分岐_ダイトレから離れ脇道を歩く_ダイトレに合流_南葛城山分岐_五つ辻754m_いわわきの道分岐_旧展望台前_東峰・きゅうざかの道分岐_ダイトレから離れ脇道を歩く_ダイトレに合流_トイレ_岩湧山897.7m_11:38展望所・昼食11:56_キトラ山790m_送電線鉄塔75_カキザコ_林道を横断_施福寺分岐_トイレ_12:57滝畑ダムバス停13:25_<バス>_14:15南海高野線河内長野駅14:29
画像はこの日歩いた南海高野線紀見峠駅から滝畑ダムバス停までのGPSログを表示。
| |
 |
|
ホトトギスの仲間。
ダイトレ、五ツ辻付近にて。
| |
 |
|
青空。
岩湧山山頂にて。涼しくて快適
| |
 |
|
クルマユリ。
岩湧山山頂付近にて。
| |
 |
|
キキョウ。
岩湧山山頂付近にて。
| |
|
9月4日(月)19:16 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 星田山_日高山_森の宝島21 |
|
 |
|
ぼって谷から登り返す。
画像は振り返って撮影。
| |
 |
|
暫く登りが続く。
| |
 |
|
登山道を示す赤や黄色のマーキングテープが見える。
| |
 |
|
尾根筋歩きとなる。
| |
 |
|
分岐に立つ道標。
「左(北) 坂登山 星田山手」と記されている。
ペットボトルに紙切れを入れて、園芸用の支柱らしき棒をペットボトルに差し込みビニールテープで巻いてある。
なかなかのアイデア。
これだと雨に濡れることはない。
材料費もほとんどかからない。
| |
|
9月3日(日)19:54 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|