| 音羽三山_展望台12 |
|
|
 稜線歩きが暫く続き、その後、小さく下る。周りはすべて植林で景色にほとんど変化はない。 稜線歩きが暫く続き、その後、小さく下る。周りはすべて植林で景色にほとんど変化はない。
| |
|
 やがて登り返すと、音羽山の山頂に到着。 やがて登り返すと、音羽山の山頂に到着。
| |
|
 展望はなく、山頂板の表示がないと、どこが山頂かわかりにくい。 展望はなく、山頂板の表示がないと、どこが山頂かわかりにくい。
| |
|
 山頂で少し休憩するが、展望もないので先に進むことに。 山頂で少し休憩するが、展望もないので先に進むことに。
| |
|
 音羽山の山頂付近はクマザサが生い茂っていたが、鞍部に向って下ると、クマザサは見えなくなり、下草がほとんど生えていない植林帯の中を歩く。 音羽山の山頂付近はクマザサが生い茂っていたが、鞍部に向って下ると、クマザサは見えなくなり、下草がほとんど生えていない植林帯の中を歩く。
| |
|
4月5日(土)20:54 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 音羽三山_展望台11 |
|
|
 昼食を済ませ、いよいよ音羽山の山頂を目指す。 昼食を済ませ、いよいよ音羽山の山頂を目指す。
| |
|
 展望台を後にして、振り返る。画像の二人は別の登山パーティー。尚、ここからの展望は、奈良県景観資産に登録されている。奈良県のHP http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=31273 展望台を後にして、振り返る。画像の二人は別の登山パーティー。尚、ここからの展望は、奈良県景観資産に登録されている。奈良県のHP http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=31273
| |
|
 一旦、谷筋へ下って、従来からある登山道に合流し、これを歩く。尚、展望台から、直に山頂へと向う踏み跡もあるらしいが、歩いたことはない。 一旦、谷筋へ下って、従来からある登山道に合流し、これを歩く。尚、展望台から、直に山頂へと向う踏み跡もあるらしいが、歩いたことはない。
| |
|
 すぐに谷筋を離れ、尾根に取り付く。暫く、九十九折に登る。 すぐに谷筋を離れ、尾根に取り付く。暫く、九十九折に登る。
| |
|
 主稜線に出ると、傾斜は緩やかになってくる。以前、下見に来た時は、展望台からの踏み跡らしき分岐があったが、この日は気付かず。踏み跡は消えたのかもしれない。 主稜線に出ると、傾斜は緩やかになってくる。以前、下見に来た時は、展望台からの踏み跡らしき分岐があったが、この日は気付かず。踏み跡は消えたのかもしれない。
| |
|
4月4日(金)21:15 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 音羽三山_展望台10 |
|
|
 昨年の夏に下見に来た時より、登山道は整備されているといった印象。尚、この道普請は、「新宮山彦ぐるーぷ」によるものと聞く。「新宮山彦ぐるーぷ」のHP http://syamabiko.web.fc2.com/ 昨年の夏に下見に来た時より、登山道は整備されているといった印象。尚、この道普請は、「新宮山彦ぐるーぷ」によるものと聞く。「新宮山彦ぐるーぷ」のHP http://syamabiko.web.fc2.com/
| |
|
 画像ではわかりにくいかもしれないが、相当急な斜面。 画像ではわかりにくいかもしれないが、相当急な斜面。
| |
|
 よじ登る、這いずり上がるといった表現がピッタリ。 よじ登る、這いずり上がるといった表現がピッタリ。
| |
|
 ようやく展望台広場に到着。展望台への取付から20分程度。程よい汗をかいた。 ようやく展望台広場に到着。展望台への取付から20分程度。程よい汗をかいた。
| |
|
 ここで眺望を楽しみながらの昼食となる。暑くも寒くもなく、絶好の登山日和。 ここで眺望を楽しみながらの昼食となる。暑くも寒くもなく、絶好の登山日和。
| |
|
4月4日(金)21:13 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 音羽三山_展望台9 |
|
|
 展望台へ至る道は、所謂、道普請で、いきなり急登となる。しかし、振り返れば展望が開けており、ゆっくりと展望を楽しみながら登ることが出来る。 展望台へ至る道は、所謂、道普請で、いきなり急登となる。しかし、振り返れば展望が開けており、ゆっくりと展望を楽しみながら登ることが出来る。
| |
|
 中央のなだらかなピークは藤原鎌足の墓とされている「御破裂山」607m。 中央のなだらかなピークは藤原鎌足の墓とされている「御破裂山」607m。
| |
|
 急登が続く。 急登が続く。
| |
|
 これは雨水を溜める器で、植栽した木々に水を遣るのだろう。 これは雨水を溜める器で、植栽した木々に水を遣るのだろう。
| |
|
 植栽されたばかりの若木。これから育てていくには、下草を刈り取るのが大変だと思う。ネットは鹿の食害から守る。 植栽されたばかりの若木。これから育てていくには、下草を刈り取るのが大変だと思う。ネットは鹿の食害から守る。
| |
|
4月3日(木)21:03 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 音羽三山_展望台8 |
|
|
 観音寺を後にする。右に見える建物は護摩祈祷所。この時、般若心経が唱えるお経が聞こえ、護摩祈祷が行われている真っ最中だった。 観音寺を後にする。右に見える建物は護摩祈祷所。この時、般若心経が唱えるお経が聞こえ、護摩祈祷が行われている真っ最中だった。
| |
|
 音羽山登山道を示す道標。 音羽山登山道を示す道標。
| |
|
 登山道脇に記念碑がある。文中にある芝房治氏は郷土史家で、私は彼の講演「音羽山観音寺と皇朝十二銭」を聞いたことがある。尚、残念ながら故人となられた。 登山道脇に記念碑がある。文中にある芝房治氏は郷土史家で、私は彼の講演「音羽山観音寺と皇朝十二銭」を聞いたことがある。尚、残念ながら故人となられた。
| |
|
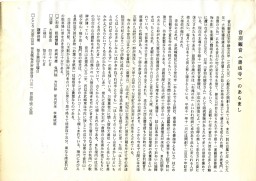 これは以前、お寺で頂戴した「音羽観音のあらまし」。 これは以前、お寺で頂戴した「音羽観音のあらまし」。
| |
|
 登山道は本格的な登りに差し掛かってすぐ、展望台への分岐となる。ここは以前からある谷筋の道ではなく、眺望が利く展望台への直登ルートを歩くことになった。 登山道は本格的な登りに差し掛かってすぐ、展望台への分岐となる。ここは以前からある谷筋の道ではなく、眺望が利く展望台への直登ルートを歩くことになった。
| |
|
4月3日(木)19:23 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 音羽三山_展望台7 |
|
|
 香久山香山寺(こうざんじ)から移されたと伝える明暦二年銘のある梵鐘。尚、香山寺は廃滅。 香久山香山寺(こうざんじ)から移されたと伝える明暦二年銘のある梵鐘。尚、香山寺は廃滅。
| |
|
 境内で休憩中の皆さん。 境内で休憩中の皆さん。
| |
|
 境内の奥に、柵で囲われたところがあり、中には花が植えてあった。あまり見かけない花なので、お寺の人に尋ねると、ユキワリソウとのこと。 境内の奥に、柵で囲われたところがあり、中には花が植えてあった。あまり見かけない花なので、お寺の人に尋ねると、ユキワリソウとのこと。
| |
|
 こちらは白い花。ニリンソウの花に似ているが、葉っぱが違う。 こちらは白い花。ニリンソウの花に似ているが、葉っぱが違う。
| |
|
 葉っぱが独特で、オキザリスの葉に似ている。 葉っぱが独特で、オキザリスの葉に似ている。
| |
|
4月2日(水)21:57 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 音羽三山_展望台6 |
|
|
 こちらは植栽されたであろうフクジュソウ。 こちらは植栽されたであろうフクジュソウ。
| |
|
 軒下に積まれた薪。 軒下に積まれた薪。
| |
|
 観音寺は尼寺で、このお人形は、左・住職(Gさん)と副住職(Sさん)だろう。 観音寺は尼寺で、このお人形は、左・住職(Gさん)と副住職(Sさん)だろう。
| |
|
 境内に建つ歌人・生田蝶介の歌碑。「人麻呂の 嘆きをぢかに 聴きており 暦日も無き 山の秋雨」 境内に建つ歌人・生田蝶介の歌碑。「人麻呂の 嘆きをぢかに 聴きており 暦日も無き 山の秋雨」
※Wikipediaより「生田 蝶介(いくた ちょうすけ、1889年5月26日-1976年5月3日)は、日本の歌人、小説家。本名・調介。山口県生まれ。早稲田大学中退。博文館の社員となり、1916年歌集『長旅』を刊行、1924年歌誌『吾妹(わぎも)』を創刊する。批評、小説も書いた。」
生田蝶介が昭和三十六年十月秋雨の中、観音寺を訪れた。
| |
|
 シイタケを栽培されている。 シイタケを栽培されている。
| |
|
4月2日(水)21:55 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 音羽三山_展望台5 |
|
|
 頭上を眺めると、画像では分かりにくいが、観音寺の建物が見えた。以前はこの場所からは見えなかった。よく見ると周りの植林が間伐されており、見通しがよくなっていた。明るくて気持ちが良い。 頭上を眺めると、画像では分かりにくいが、観音寺の建物が見えた。以前はこの場所からは見えなかった。よく見ると周りの植林が間伐されており、見通しがよくなっていた。明るくて気持ちが良い。
| |
|
 左手に階段が現れる。観音寺の境内へはこの階段を登る。 左手に階段が現れる。観音寺の境内へはこの階段を登る。
| |
|
 階段を登り詰めると本堂。 階段を登り詰めると本堂。
| |
|
 音羽山と彫られた手水鉢。文政十一年の寄進。この手水鉢は、四人の力士で支えられている脚が見える。 音羽山と彫られた手水鉢。文政十一年の寄進。この手水鉢は、四人の力士で支えられている脚が見える。
| |
|
 境内の奥の方へ入って行くと、フキノトウがあった。植栽されたものかもしれない。 境内の奥の方へ入って行くと、フキノトウがあった。植栽されたものかもしれない。
| |
|
4月1日(火)20:57 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|
| 音羽三山_展望台4 |
|
|
 植林帯の中に続く舗装された道を歩く。杉の花粉が気になるので、この日、私はマスクをつけてきた。 植林帯の中に続く舗装された道を歩く。杉の花粉が気になるので、この日、私はマスクをつけてきた。
| |
|
 道標。「左 たふのミ祢 音羽山観世音」。裏には安政二年六月吉日と刻まれている。安政二年は1855年。この道標は登ってきた人の道しるべではなく、観音寺から下ってきた人の為に、多武峯へ行く道を示している。 道標。「左 たふのミ祢 音羽山観世音」。裏には安政二年六月吉日と刻まれている。安政二年は1855年。この道標は登ってきた人の道しるべではなく、観音寺から下ってきた人の為に、多武峯へ行く道を示している。
| |
|
 やがて、石で作られた小さな橋、「無常橋」を渡る。この橋には建立した日が刻まれいている。明治三十九年四月十七日。 やがて、石で作られた小さな橋、「無常橋」を渡る。この橋には建立した日が刻まれいている。明治三十九年四月十七日。
| |
|
 お二人とも、お辞儀をしているように見えるが、そうではなく、傾斜が急なので、自然とこのような格好になる。 お二人とも、お辞儀をしているように見えるが、そうではなく、傾斜が急なので、自然とこのような格好になる。
| |
|
 丁石を見ながら登るのもよいが、このような絵を眺めながら歩くのも楽しい。 丁石を見ながら登るのもよいが、このような絵を眺めながら歩くのも楽しい。
| |
|
4月1日(火)19:32 | トラックバック(0) | コメント(0) | 山歩き | 管理
|